メンタルヘルス入門
2025.09.10
大人の発達障害とは?特徴や向き合い方、分類を紹介

大人の発達障害は、仕事や家庭など社会生活の中で「なぜかうまくいかない」「周囲とズレを感じる」といった悩みをきっかけに気づくことが多い特性です。
子どもの頃は目立たなかった困難が、責任や役割が増すことで表面化し、初めて発達障害と診断されるケースもあります。生きづらさや対人関係の苦労を抱えている方も多く、適切な医療機関の受診やサポートが求められます。
この記事では、大人の発達障害の主な特徴や分類、仕事や日常生活で現れやすい影響、医療機関への相談方法などについて紹介します。大人の発達障害で困りごとを抱え、対策を考えている人は、ぜひ参考にしてください。
大人の発達障害の代表的な特徴

発達障害は先天的な特性であり、個人差はありますが、日常生活や仕事の現場でその特性が具体的に現れることが少なくありません。
ここでは、大人の発達障害に見られる代表的な特徴について、主に社会生活、コミュニケーション、感覚面、グレーゾーンの4つの視点から紹介します。
社会生活で現れる特有の困りごと
大人の発達障害では、社会生活において「優先順位がつけにくい」「指示通りに動けない」「空気が読めない」といった困りごとがよく見られます。
以下でそれぞれの特徴を見てみましょう。
| 困りごと | 内容 |
|---|---|
| 優先順位がつけにくい | ・仕事や家庭で何を優先するべきか判断が難しい ・効率的に進められないことがある |
| 指示通りに動けない | 指示された仕事を言われた内容通りに遂行できない場面がある |
| 空気が読めない | ・会話で相手の意図をうまく読み取れない ・職場や集団で雰囲気に合わない言動をする |
このような行動は、能力や性格が根本的な原因ではなく、発達障害が影響を及ぼしていることも多いです。
コミュニケーション面での特徴
発達障害のある人は、コミュニケーション面でも特有の困りごとを感じることがあります。
非言語コミュニケーションの苦手さや会話の一方通行、比喩・冗談への理解不足などが代表的です。
以下でそれぞれの特徴を見てみましょう。
| 困りごと | 内容 |
|---|---|
| 非言語コミュニケーションが苦手 | 視線や表情、身振りを使った相互のやりとりが苦手なことがある |
| 一方通行になりやすい | 自分の話したいことに没頭してしまう |
| 比喩や冗談が分かりにくい | 言葉を文字通りに受け取りやすい |
このような特性から、言葉での説明がない、相手の立場に配慮するといった状況や、抽象的な表現への理解不足などが原因で困りごとを抱えるケースが見られます。
感覚の過敏さや鈍感さ
感覚が平均よりも過敏であったり、または逆に鈍感であったりすることも、発達障害のある人の特徴です。
例えば、音や光、におい、肌触りなど特定の刺激に過敏に反応することがあります。周囲の雑音が気になり集中しにくい、衣服の着心地が気になって落ち着かないなどが代表的です。
一方、逆に痛みや温度差、味覚などへの感覚が人より鈍い場合もあります。そのため、けがや体調不良に気づきにくく、周囲から指摘されるまで自覚しないケースも見られます。
ただし、「発達障害だから必ず感覚過敏、必ず鈍感」というわけではなく、あくまで個人差がある点は理解しておきましょう。
発達障害のグレーゾーンとは?
発達障害のグレーゾーンとは、発達障害の診断を受けていないものの、発達障害の特性を持ち、日常生活で困りごとや生きづらさを感じる状態です。
以下のような特徴があります。
- 発達障害の特性を持っている
- 診断基準の一部には当てはまるが、すべてを満たしていない
医学的に正式に発達障害だと診断されていないため、公的なサポートが受けられず、周囲にも理解してもらいにくいという独特の悩みを抱える人も少なくありません。
発達障害の分類と特徴
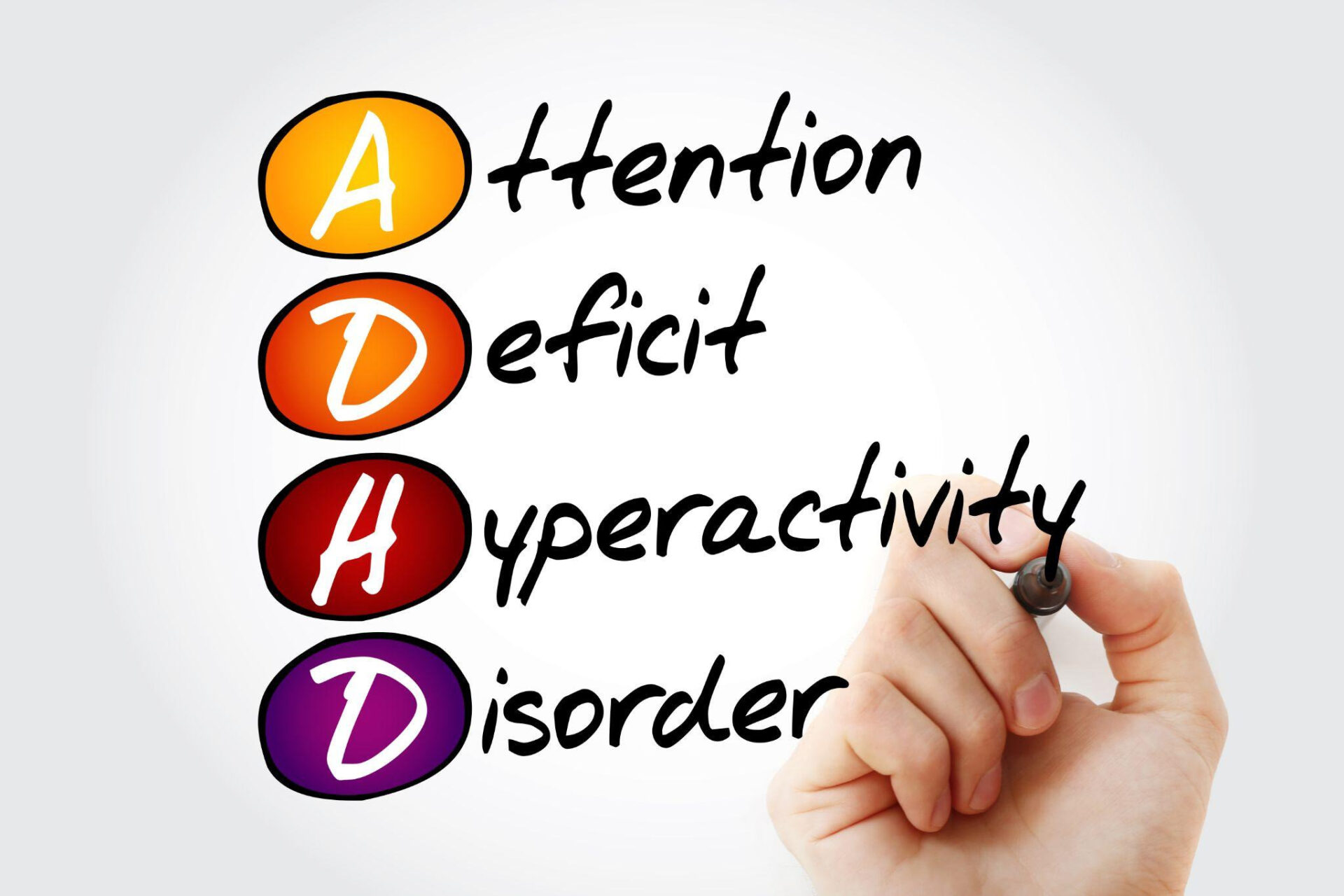
発達障害は主に自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、限局性学習症(SLD)の3つに分類されます。
ここでは、それぞれの特徴を紹介します。
自閉症スペクトラム(ASD)
自閉スペクトラム(ASD)は社会的コミュニケーションが苦手で、興味や行動が一部に強く偏ることが多いタイプです。
言葉や視線、表情などを用いたやりとりが苦手で、人との関わりで誤解が生じやすい傾向があります。
さらに、狭い範囲に強いこだわりを持つ、特定のテーマに没頭するなどの特性もあるため、独特の行動パターンが見られる点も特徴です。また、感覚に過敏さ・鈍感さが見られる場合もあります。
注意欠如・多動症(ADHD)
注意欠如・多動症(ADHD)は、集中できない「不注意」や、じっとしていられない「多動」、衝動的に行動する「衝動性」などが目立つ特性です。
成人の場合、落ち着きのなさよりも、不注意が多く見られることが少なくありません。不注意が強い人は集中が続かず、うっかりミスや忘れ物が多いことが代表的なケースです。
多動はじっとしていられず、そわそわと身体を動かしてしまいます。衝動性では、思いつきの行動や思ったことをそのまま口にしてしまうなどがあります。
限局性学習症(SLD)
限局性学習症(SLD)は学習障害(LD)とも呼ばれ、全般的な知能に問題はありませんが、特定の学習に困難がある特性です。
理解力や記憶力自体は正常範囲で、知的能力に問題はないものの、「読む」「書く」「計算する」などの特定の学習行為だけに困難が現れます。例えば、文字を見ても正しく読めない、計算ミスが多い、文章を書くのに時間がかかるなどの症状が出るケースが多いです。
一部の学習活動に苦手意識が強く表れるため、学習の遅れや業務の理解不足などの原因になることがあります。
自己診断ではなく必ず医療機関での診断を
生活や仕事で困難を感じている場合や、発達障害の疑いがあると感じた場合には、安易に自己判断せず、専門の医療機関を早めに受診しましょう。
自治体や支援センター、相談窓口などでも困りごとについての相談は可能ですが、診断や治療の判断は行えません。インターネットの自己診断やチェックリストは、自分の傾向を知る参考にはなりますが、医学的な診断としては不十分です。
その点、精神科や心療内科などの専門医が行う診察・検査・診断は信頼性と専門性が高く、信頼できる根拠が提示されます。医師による面談や聞き取り、心理検査などを経て総合的に診断されるため、正しい理解と適切な支援につながりやすくなるでしょう。
大人の発達障害が仕事に及ぼす影響と対策

発達障害は、職場で努力不足と誤解されることがあります。その結果、職場でのストレスが増え、精神的な不調を招く可能性も否定できません。
ここでは、大人の発達障害が仕事に及ぼす影響や対策について紹介します。
見えにくい特性で誤解されることも
発達障害の特性は内面的・抽象的なものが多く、周囲には分かりにくい傾向があります。
例えば、努力しているにもかかわらず、社会的評価では「努力不足」と受け取られてしまうケースも少なくありません。職場では隠れた特性が原因でミスや遅れが生じるため、周囲から否定的に見られるリスクが高まります。
また、職場で発達障害への理解が不足している場合にも、発達障害のある人への誤解が生まれやすくなるでしょう。
ストレスやトラブルを抱えやすい
発達障害の特性による困りごとが続くと、仕事でのストレスや対人トラブルが増え、疲弊しやすくなります。
理解のない職場で叱責を受け続けると自信を失い、結果的にうつ病や適応障害などの二次障害につながる恐れもあります。自分が「頑張ってもできない」という状態に気づいたら、早めに支援を求めることが重要です。
業務内容と特性のミスマッチが原因になっていることもあるため、職場に理解を求め、労働環境の改善を考えるのも役立つでしょう。
職場での適応に役立つ工夫が望ましい
職場では、個人の特性に合わせた配慮や環境調整が適応を助けます。
例えば、大人の発達障害では以下のような方法が効果的なケースもあります。
- 仕事のルールや手順を明確に提示してもらう
- 視覚的な指示(図や表、メモなど)を取り入れる
- 作業工程を細かく分けて、段階ごとに説明してもらう など
感覚過敏がある場合には、イヤーマフや静かな作業スペースを使うなどの工夫や調整を試みましょう。
また、行政のジョブコーチ支援など、発達障害者向けの就労支援制度もあるため、積極的な利用もおすすめです。例えば地域の障害者職業センターでは、職場での困りごとへの助言やアドバイスを受けられます。
このような対策によって、自分に合った働き方を見つけやすくなります。
周囲の理解とサポートの重要性
発達障害のある人が社会人としてストレスを軽減しながら働き続けるには、周囲の理解と協力が欠かせません。
家族や同僚が特性を理解し、適切なサポートや配慮を行うことで、困りごとやストレスの軽減が可能になります。
例えば、以下のようなサポートが効果を発揮するでしょう。
- 業務の優先順位を共有する
- コミュニケーション方法を工夫する など
理解が不十分なままでは、互いにフラストレーションが高まりやすく、前述のような二次障害リスクが増加しかねません。職場で困ったことがあれば、まず上司や人事、周囲の信頼できる人に相談し、協力を求めることが大切です。
自分が発達障害かもしれないと思ったら

「もしかして大人の発達障害では」と思い当たることがあれば、セルフチェックや周囲への相談、医療機関の受診などを考えてみましょう。
ここでは、自分が発達障害ではないかと思った時の行動について紹介します。
セルフチェックで振り返る
発達障害の疑いがある場合は、セルフチェック(質問票)を利用してみましょう。
例えば、大人のADHDの自己記入式症状チェックリストとして「ASRS-v1.1」が知られています。
ただし、セルフチェックはあくまで簡易にすぎず、正式な診断ではありません。「セルフチェックの結果だと自分は○○だ」と決めつけずに、正式な診断を出すため、必ず医療機関を受診してください。セルフチェックはあくまで参考にして、「その傾向がありそうだから受診してみよう」と考えるきっかけにしましょう。
周囲のアドバイスを受けてみる
発達障害は自覚しにくい特性が多いため、自分だけでは判断できないこともあります。
家族や友人、同僚など信頼できる人に相談し、自分の困りごとや悩みを共有して、意見を聞いてみましょう。身近な人の目線で指摘されることが、自身の気づきにつながる場合があります。
診断はあくまで医師が行いますが、身近な理解者の視点や見方が問題解決の手がかりになることもあります。
具体的な「困りごと」を考えてみる
日常や仕事で自分が困っていることを具体的に書き出してみましょう。
例えば、次のようなことは発達障害で発現しやすい困りごとです。
- 会議の予定を忘れてしまう
- 仕事に優先順位をつけられない
- 感覚過敏でオフィスの音がつらい など
このような具体例は、自分の悩みを理解するきっかけになるだけではなく、医療機関を受診した時に、医師が傾向や問題点を把握する貴重な情報になります。
医療機関を受診する
発達障害の特性が生活に支障を来す場合や、セルフチェックで発達障害の可能性を示す結果が出た場合は、精神科・心療内科など、発達障害に適した診療科を受診しましょう。
医師はこれまでの生育歴や困りごとを詳しく聞き、適切な診断を行います。診断を受けることで、必要な支援や対処法が見えてくる人もいるでしょう。
中には「病院へ行くのは嫌だ」「偏見の目で見られるかも」と思う人もいるかもしれません。しかし、心配はいりません。診断がついてもそれはレッテルではなく、将来の選択肢を増やすための手段です。
ストレスを軽減し、患者さん本人も周囲の人も快適に生きやすい環境を整えるためには、医療機関で診断を受け、特性や現在の環境に相応しい対策や支援を知ることが大切です。
まとめ
大人の発達障害は、生まれつきの特性によるもので、対人関係や感覚、学習面に独特の困難をもたらします。仕事や日常生活でミスやトラブルが続くようなら医療機関で相談し、原因を明らかにすることが重要です。
医師の診断や周囲の理解・支援を受けながら、自分の特性に合った工夫を積み重ねることで、仕事や人間関係にうまく適応できる可能性が高まります。一人で悩まず、適切な情報とサポートを得て自分に合った対策を取りましょう。
メンタルクリニック下北沢では、大人の発達障害について積極的なサポートをしています。「大人の発達障害かも」「セルフチェックでその傾向が…」と感じるようなことがあれば、対策のひとつとして受診してみてはいかがでしょうか。どうぞお気軽にご相談ください。
この記事の監修者
メンタルクリニック下北沢
院長・精神保健指定医
堀江 宇志
- 【所属学会】
-
- 日本精神神経学会
- 日本認知症学会
- 日本臨床睡眠学会
- 日本学校メンタルヘルス学会
- 【経歴】
-
京都大学理学部入学後、山口大学医学部に転学。卒業後、成康会堤小倉病院、FLATS ヒルサイドクリニック、八王子メンタルクリニック院長、佐藤メンタルクリニック副院長、下北沢メンタルケアクリニック院長等を経て現職。


