メンタルヘルス入門
2025.09.10
子供の発達障害の特徴は?種類別チェックリストも紹介

近年、子供の発達障害が注目されています。自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、限局性学習症(SLD)など、多様な特性に関心が向けられることが増えました。
発達障害は幼少期から兆候が現れやすい一方で、気付きにくいケースや誤解されてしまう場面も少なくありません。発達障害の種類や特性、サポート機関についてを知っておくことは、早期発見・早期支援につながり、本人や家族の安心にも役立ちます。
この記事では、主な発達障害の特徴やチェックリスト、増加の背景、早期発見の重要性、公的支援などについて紹介します。子供の発達障害について詳しく知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
発達障害の種類や主な特徴

発達障害には大きく分けて自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、限局性学習症(SLD)の3つがあります。
ここでは、それぞれのタイプで見られる主な特徴について紹介します。
自閉症スペクトラム(ASD)
自閉スペクトラム症の子供には、社会的なコミュニケーションの困難と限定的・反復的な行動様式を持つ特徴が多く見られます。
普段の生活や集団の中で、以下のような傾向が現れることが多いです。
- 人と遊ぶより1人でいることが多い
- 目が合いにくい
- 相手の気持ちや場の雰囲気を読み取りにくい
- 同じ遊びや動作を繰り返す
- 急な予定変更や新しいことが苦手
- 音や光、服の感触などに敏感
このような特徴は個人差があり、子供によって現れ方が異なります。気になる様子があれば、医療機関や専門家への相談を検討しましょう。
注意欠如・多動症(ADHD)
注意欠如・多動症(ADHD)は「不注意」「多動性」「衝動性」を主な特徴とする発達障害です。
症状は子供ごとに異なりますが、それぞれ以下のような傾向が代表的です。
| 特徴 | 傾向 |
|---|---|
| 不注意 | ・課題や作業に集中できない ・うっかりミスが多い ・指示を聞き漏らす ・忘れ物が多い |
| 多動性 | ・授業中に席を離れてしまう ・手足をそわそわ動かす ・静かにし続けられない ・しゃべりすぎる |
| 衝動性 | ・順番を待てない ・思いつきで発言・行動する ・他人の会話や遊びに割り込む |
このような特性は低年齢のうちに目立ちやすいですが、年齢とともに傾向が変化することもあり、「落ち着きがない」より「注意力や計画性のなさ」や「衝動的な失敗」といった方面で顕著になるケースもあります。
限局性学習症(SLD)
限局性学習症(SLD)は知的発達に遅れがないにもかかわらず、特定の学習分野(読む・書く・計算など)が苦手な発達障害です。学習障害(LD)とも呼ばれます。
SLDには以下のような特徴があります。
| 特徴 | 傾向 |
|---|---|
| 読字障害(ディスレクシア) | ・文字が歪んで見える ・文章の読み飛ばしや読み間違いが多い |
| 書字表出障害(ディスグラフィア) | ・書き順違いや鏡文字 ・文字の転倒や逆転 |
| 算数障害(ディスカリキュリア) | ・数字や記号、量の概念を理解しづらい ・計算が苦手 |
知能が平均、または平均以上でも、「音読が極端に遅い」「黒板の字をノートに書き写せない」「九九や時計が覚えられない」といった困難を抱えやすい傾向があります。
本人の努力不足や親のしつけの問題、知的障害と誤解されやすく、周囲の正しい理解が求められます。
発達障害が増えたと言われる理由
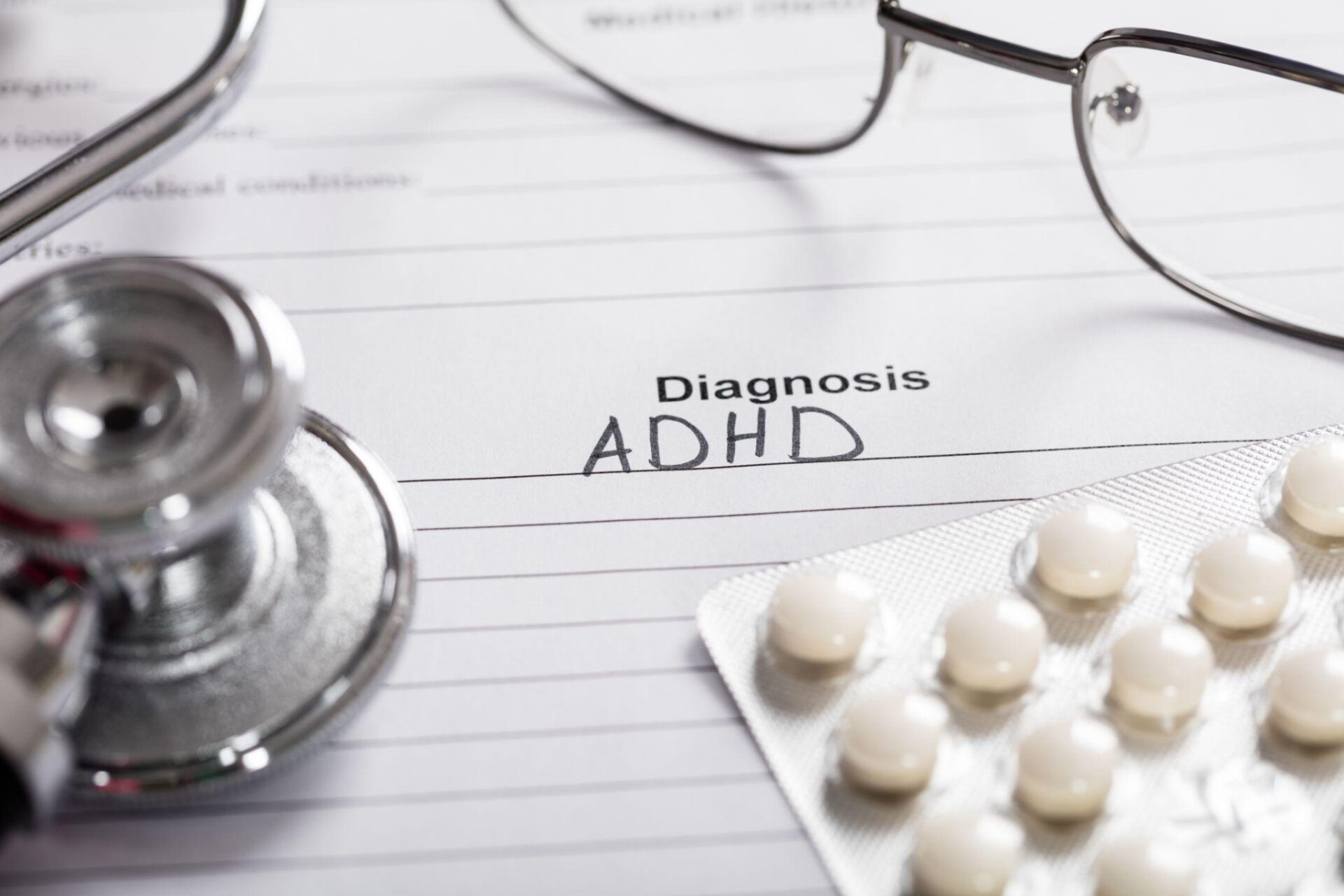
近年、発達障害の子供が増えていると言われていますが、その背景にはさまざまな要因があります。特に影響しているのは以下の要素だと考えられます。
- 診断基準の見直し
- 発達障害への理解や認知の広がり
- 自治体の集団検診などでの指摘
2013年にDSM-5(米国精神医学会の診断基準)が改定され、発達障害の範囲が広がりました。これにより、軽度のケースも診断されるようになり、「発達障害の子供が増えた」という結果につながっています。
また、発達障害についての社会的な理解や認知が進み、医療や教育現場での啓発や相談体制が充実したことも関係しています。以前は見過ごされていた困りごとも注目されるようになり、発達障害の特徴として気付かれる機会が増加しました。
さらに、自治体の集団健診や就学時のチェックリストが普及し、早期発見につながるケースも見られます。
そのため、「最近になって増えた」のではなく、「今まで見過ごされていた人も適切なケアが受けられるようになった」というのが実情でしょう。
発達障害のチェックリスト

発達障害の早期発見には、家庭や教育現場で使えるスクリーニングチェックリストが役立ちます。ここでは、特性ごとのチェックリストについて紹介します。
ただし、どのリストも正式な診断ではなく「受診・相談のきっかけ」として活用するものです。結果が当てはまる場合も、必ず医療機関や専門機関で詳しい評価を受けてください。
自閉症スペクトラムのチェック(ASD)
自閉スペクトラム症(ASD)は、成長にともなって少しずつ現れる特徴があり、親が気付きやすいサインがいくつかあります。
乳児期、幼児期で見られる代表的なサインを以下にまとめました。一例として参考にしてください。
| 時期 | 代表的なサイン |
|---|---|
| 乳児期 | ・目が合いにくい ・あやした時の笑顔や表情の反応が乏しい ・親の呼びかけに反応しにくい ・人見知りや後追いが少ない ・一人遊びが多い |
| 幼児期 | ・言葉の発達が遅い、または急に使わなくなる ・指差しやジェスチャーで物事を伝えない ・他の子供との関わりが少ない ・同じ遊びや動作を繰り返す ・ルールや順番へのこだわりが強い ・音や感触、光などに過敏、または無関心 |
| 学童期 | ・友達とうまく遊べない ・相手の気持ちや空気を読み取るのが難しい ・会話が一方的になりやすい ・予定やルールが変わると強いストレスを感じる ・興味があることにばかり熱中する ・感覚の敏感さや鈍感さが続く |
これらの兆候が複数見られるからといって、必ずしもすべての子供がASDとは限りませんが、発達の視点から配慮が必要なケースもあります。
注意欠如・多動症のチェック(ADHD)
注意欠如・多動症(ADHD)の評価には、5歳~18歳の子供向けに家庭や学校で記入するADHD-RS(18項目)が広く使われています。
「不注意」と「多動性・衝動性」の2つの側面から行動を評価する方法です。
以下に主な質問項目の一部を紹介します。
| タイプ | 質問例 |
|---|---|
| 不注意 | ・授業中などに細かいところでうっかりミスが多い ・課題に集中し続けるのが難しい ・物をよく失くす、忘れ物が多い |
| 多動性・衝動性 | ・授業中に席を立つ、じっとしていられない ・じっとしていられず「エンジンがかかったように動く」 ・順番を待てず、話や指示が終わる前に口を挟む |
ADHD-RSは、各項目を「ない(0)」「ときどき(1)」「しばしば(2)」「非常にしばしば(3)」の4段階で評価します。
不注意領域(9項目)、多動・衝動領域(9項目)の合計点を算出する方法で使われます。
有力なツールであることは事実ですが、複雑なため個人での判断は困難です。あくまで参考にとどめ、気になる場合には必ず専門医の診断を受けましょう。
限局性学習症(SLD)
限局性学習症(SLD)は、前述の通り、知的発達に大きな遅れがないにもかかわらず、「読む」「書く」「計算する」といった特定の学習分野で困りごとが現れます。
以下にそれぞれの困りごとについて、親や保護者に注目してほしい特徴をまとめました。
| 分類 | 特徴 |
|---|---|
| 読字障害(ディスレクシア) | ・文字や文章を読むのに極端に時間がかかる ・読んでいる行や単語をよく飛ばしてしまう ・音読が苦手で、内容を理解するのに苦労する |
| 書字表出障害(ディスグラフィア) | ・ひらがなや漢字の形を正しく書けない ・文字の大きさや位置がバラバラになる ・鏡文字が見られる |
| 算数障害(ディスカリキュリア) | ・簡単な計算や九九がなかなか覚えられない ・時計の読み方や分数の理解に時間がかかる ・数字や記号の書き間違い、読み間違いが多い |
小学校入学後、教室での勉強や宿題を通して初めて気付かれることも多く、早期発見や周囲の理解、サポートが重要になります。
チェックリストはあくまで参考に
ASD・ADHD・SLDそれぞれの特性は重なり合うこともあり、家庭や学校で見られる特徴と医学的診断が必ずしも一致するとは限りません。
また、「このリストに該当する=発達障害」という自己判断は避けましょう。
診断や支援方法の決定には、小児科・児童精神科・臨床心理士などによる専門的で多面的な評価が必要です。ご家庭では、あくまで「気付きのきっかけ」としてチェックリストを利用しましょう。
子供の発達障害は早期発見が重要

特性から生じる問題行動や困りごとは、深刻化する前に適切な支援を受けることにより、本人・家族・学校生活のすべてでメリットがあります。
ここでは、発達障害の早期発見・早期対応の重要性について紹介します。
学習や生活習慣のサポートにつながる
子供が発達障害であると分かれば、学校での合理的配慮や、特別支援学級・通級指導などの対応が早期に実現します。
家庭でも、スケジュール可視化・生活ルール明確化・タスク分割など、特性に応じたサポートを実践し、子供の頃から習慣化しやすくなるでしょう。本人の得意・不得意が明確になり、苦手を補う支援(ICT活用、マンツーマン指導、感覚過敏への環境調整など)も受けやすくなります。
将来を見据えた長期的なトレーニングができる
早期に気付くことで、将来の自立や社会参加に必要なトレーニングを段階的に進められます。
例えば、以下のような訓練は、早期にスタートすることが望ましいです。
- コミュニケーション訓練
- ソーシャルスキルトレーニング
- 学習支援
- 自己理解の促進 など
このような訓練を実践することによって、幼少期から本人主体の支援計画作成が可能になり、卒業後の働き方や生活習慣にも役立ちます。
人間関係の構築がしやすくなる
支援の工夫や配慮により、家族や友人、教師とのコミュニケーションを円滑に取れるようになります。
例えば、ASDの子供にはピクトグラムのような視覚的サポートが、ADHDの子供には短時間で切り替えられるタスク設計などが有効です。このような配慮の積み重ねで、困りごとによる孤立や二次障害(うつ・不登校)の予防につながります。
親だけが抱え込まずに済む
発達障害の早期支援により、家庭が孤立せずに、医療・福祉・教育機関と連携して子育てに取り組めます。
保護者向け相談会やペアレントトレーニング、家族支援プログラムなどを活用することで、悩みの共有やストレス軽減が期待できます。子育ての負担感を減らすことは、家庭全体のQOL向上にも寄与するでしょう。
子供の発達障害を支援する機関

子供の様子で発達障害の可能性を感じたら、早めに相談機関や医療機関を利用しましょう。
ここでは、子供の発達障害が相談できる代表的な支援先を紹介します。
自治体の福祉科
市区町村の福祉科やこども課、保健センターでは、発達障害の相談・支援・療育に関する窓口が設置されています。
保健師やソーシャルワーカーが、家庭や学校との連携、障害福祉サービスの申請、療育手帳取得の手続きなどを支援することで、親や家族の負担が軽減され、困りごとの解決もしやすくなります。
自治体によっては発達障害児のためのサポート事業や親子教室も実施しているため、お住まいの自治体の公式サイトなどでぜひ確認してください。
発達障害者支援センター
発達障害者支援センターは、全国に97か所設置されている公的機関です。(令和2年5月時点のデータ)
発達障害児や発達障害者、その家族を対象にしており、以下のような支援が受けられます。
- 困りごとの相談
- 発達障害に関する情報提供
- 就学・就労支援
- 学校や医療との連携調整 など
臨床心理士や相談員などの専門職が対応し、診断や療育の専門機関への紹介も可能です。
医療機関
発達障害の診断や医学的支援は、小児科・児童精神科・小児神経科・発達外来などで行われます。
必要に応じて心理検査や発達検査が行われ、二次障害の有無などについての確認も可能です。
医療機関で診断を受けると、学校や自治体との連携がよりスムーズになります。特別支援教育や障害福祉サービスの利用がしやすくなるため、お子さんの様子で気になる点があれば、一度相談してみることをおすすめします。
まとめ
子供の発達障害は、早期発見・早期支援が求められます。必要な時は支援機関に相談し、正しい情報とネットワークを活用してください。
自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、限局性学習症それぞれに特徴があり、家庭や教育現場のチェックリストを活用して気付きを得ることは重要です。ただし、チェックリストの結果による自己判断ではなく、結果を「きっかけ」にして、医療や福祉、教育などの専門機関に相談することを強くおすすめします。
メンタルクリニック下北沢では、子供の発達障害について、医師による幅広いサポートをご提供しています。また、発達障害への支援制度や教育についても、疑問やご不安があれば適切なご案内が可能です。小さなことでも「もしかして」と思えるようなサインがあれば、見逃さずに早めにご相談ください。
この記事の監修者
メンタルクリニック下北沢
院長・精神保健指定医
堀江 宇志
- 【所属学会】
-
- 日本精神神経学会
- 日本認知症学会
- 日本臨床睡眠学会
- 日本学校メンタルヘルス学会
- 【経歴】
-
京都大学理学部入学後、山口大学医学部に転学。卒業後、成康会堤小倉病院、FLATS ヒルサイドクリニック、八王子メンタルクリニック院長、佐藤メンタルクリニック副院長、下北沢メンタルケアクリニック院長等を経て現職。


